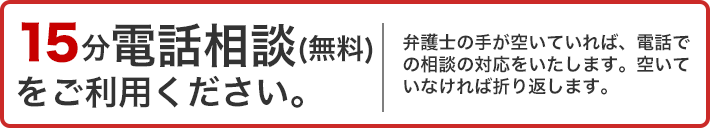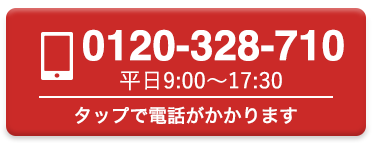Q&A
1.法人破産の法律相談と費用
Q 相談料はいくらですか?
A 初回の法律相談(60分)は無料ですので相談料はかかりません。なお、60分を過ぎても10分~20分程度では通常費用をいただいておりませんので、お気軽にご相談ください。
Q 法人の経営状態が悪化していますが、どのようなタイミングで弁護士に相談すればいいのでしょうか?
A 法人の経営状態に不安を感じた時点で一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。弁護士に相談することにより、法人の客観的な状態を把握し、今後の対応を見極めることができます。
他方で、手持ち資金を使い果たしてから弁護士に相談することは絶対に避けてください。法人に資金がないと破産の手続さえもできず、経済的再生が困難になります。
Q 相談可能な時間帯を教えてください。
A 法律相談の対応時間は平日10時~17時30分です。ご相談いただければ、17時30分以降の対応も可能ですが、法人破産の相談は法人経営に関する重要な意思決定をする場面ですので、日常業務で疲れ切った夕方・夜間ではなく、心身ともに余裕のある時間帯での相談をお勧めします。
Q 土日の相談は可能です?
A 毎月第3土曜日の午後に相談会を実施しておりますので、この枠でしたら対応可能です。その他の土日は休業日となっております。
Q 相談時にどのような資料を準備すればよいでしょうか?
A 法人税の申告書3期分、過去1年分の通帳、法人の登記簿謄本、債権者の一覧表をご準備ください。
Q 弁護士費用はどれくらいかかりますか?
A 法人破産の場合、通常、連帯保証をしている代表者も破産をすることになります。そのため、弁護士費用は法人破産分に加えて、代表者の破産分も必要になります。法人破産と代表者の破産の費用で最低80万円が必要になります。
また、破産手続では、裁判所に予納金を納めるため、最低でも法人20万円、代表者5万円が必要になります。弁護士費用は事案により異なりますので、ご相談後見積もりをさせていただきます。
弁護士費用・予納金を確保しないことには、破産手続をとりようがありませんので、早めのご相談をお勧めします。
Q 弁護士費用の分割は可能ですか?
A 法人破産案件における弁護士費用の分割は原則お断りしています。もっとも、売掛金や法人資産の売却により弁護士費用を確保することが可能と見込まれる場合は、案件着手後の支払いにも対応しております。
Q 資金繰りが厳しく弁護士費用を捻出する余裕がありませんが、どうしたらよいでしょうか?
A 全く売上(入金)がないという場合でなければ、資金繰りが厳しいのは入金より支払いが多いことが原因です。法人の破産を視野にいれた場合は、支払を停止し、他方、売掛金は回収することにより一時的に手持資金を増やすことができます。このようにして弁護士費用等の法人破産の資金を捻出することができます。具体的な対応は個々の事案ごとに検討しますので、ご相談ください。
Q 法テラスは利用可能ですか?
A 申し訳ございませんが、弊所独自の基準により弁護士費用を見積もっているため、法テラスの利用はお断りしております。なお、法テラスを利用しない場合でも弁護士費用を確保する方法はありますので、費用の捻出方法も含めて弁護士にご相談ください。
2.破産後の生活について
Q 法人が破産すると今後生活していくことができません。多少無理をしてでも法人を続けたほうがいいでしょうか?
A 法人経営者にとって、法人の破産=生活の糧がなくなるということを意味するため、無理してでも法人を続けようという考えがでてくることは理解できます。
しかし、経営改善の見込みがないままに、親族・知人からの借金を重ねたり、取引先への支払いを滞納し続けても周囲に迷惑をかけるだけです。また、無理を重ねて心身ともに疲弊しきってから破産をしても生活再建が難しくなってしまいます。もし援助をしてくれる親族・知人がいる場合は、むしろ、破産後の生活再建についての協力を求めるべきです。
破産するか否かの見極めについては弁護士にご相談ください。
Q 破産した場合、財産はすべて処分されてしまうのでしょうか?
A 破産した場合の財産処分は法人と個人で異なります。
法人の破産の場合、法人は解散して法的には存在しなくなりますので、法人の財産は全て処分されます。
他方、個人の場合は、破産後も生活していく必要があるため、生活用品に加え、原則99万円までの財産を手元に残すことができます(自由財産拡張申立)。
Q 手元資金が厳しくなってきたので長年かけてきた「小規模事業共済」を解約する予定ですが問題ありませんか?
A 絶対に解約しないでください。
小規模事業共済の解約金は、原則「全額」差押禁止財産とされており(小規模事業共済法15条本文)、破産した場合でも解約金相当額を全額手元に残すことができます。例えば、10年以上小規模事業共済に加入していれば、掛金尾額にもよりますが解約金が200万円~300万円にはなると見込まれます。この場合、解約金全額に加えて、更に自由財産を拡張の申し立てができます(どの程度まで拡張が認められるかは事案により変わります)。
他方で、小規模企業共済を解約してしまうと、その解約金は現金又は預貯金の扱いになるため、99万円までしか手元に残すことができません。
このように、小規模事業共済は破産後の生活再建に有益ですので、絶対に解約しないでください。逆に言えば、小規模企業共済を解約するほどに追い込まれた場合は、法人の破産を検討する必要があります。
Q 破産しても仕事をして大丈夫でしょうか?
A もちろん大丈夫です。法人破産の場合、代表者とその家族の生活再建が一番の問題になりますので、速やか仕事を見つけてください。
Q 破産後に同じような事業をしても問題はありませんか?
A 理論上は問題ないのですが、実際の破産手続との関係では難しい問題を含んできます。必ず弁護士と相談しながら進めてください。
長年経営してきた法人を破産させた場合、代表者の方から、それまでの人脈・経験を生かして再度同じ事業に関与したいとの希望が示されることがあります。このような希望はもっともであり、年齢によっては全く未経験の業界で再就職が困難な場合もあることから、現実的な希望とも言えます。
他方で、破産した法人と同じ事業を始めた場合、破産した法人の資金・什器備品の流用や売掛金債権の付け替えを疑われる場合があり、法人の破産手続きに悪影響を及ぼすことがあります。
そこで、このような事態を避けるため、必ず破産申し立てを担当する弁護士に相談しながら対応することをお勧めします。
Q 家族に迷惑を掛けたくないので破産はしたくありません。
A 法人が事実上破産状態にある場合、すでに家族に迷惑が掛かっています。また、このような状態を継続すれば家族に迷惑をかける時間が長くなります。家族に与える悪影響を少しでも短くするために現実的な対応を検討すべきです。
家族にどのような迷惑を掛けることを心配しているのか、その内容から弁護士にご相談ください。
3.破産のメリット・デメリット
Q 法人破産のメリットを教えてください。
A 法人破産の最大のメリットは、借入金などの債務の支払義務がなくなることです。債務を破産法に基づいて適法に処理するため、債権者から督促を受けることがなくなります。
また、債権者側としては、債務が破産法に基づいて処理されたことにより、税務上損金計上できるというメリットが生じます。
代表者個人としてのメリットも、法人破産と同様、連帯保証債務等の支払義務を法的に処理できることです。
破産手続が開始以降の収入は、債務の支払いに充てる必要がなくなり、全額生活資金にあてることができるようになります。
Q 法人破産のデメリットを教えてください。
A 法人破産は、事業体としての法人が消滅することになるため、破産する法人の利害関係人に影響を与えるというデメリットがあります。
具体的には、
- 法人の債務の連帯保証人に請求がされ連帯保証人が債務の支払いをすることになり、場合によっては自己破産を余儀なくされる。
- 法人の資産は全て換価され法人が営んでいた事業は原則消滅する。
- ②に伴い従業員は解雇される。
- 買掛金の支払いは事実上できない(破産の場合配当ができる場合でもその配当率は、通常債権額の数パーセントです)。場合によっては、連鎖倒産を引き起こす。
- 仕掛りの受注案件がある場合は取引先に損害を発生させる。
等があります。
もっとも、法人破産を選択しなくても、事実上倒産状態にある法人であれば、このような事態は早晩発生することから、法人破産特有のデメリットとは言えない面があります。破産を選択するか否かにかかわらず、法人の事業が停止すれば利害関係人に影響が生じるのは避けられない以上、その影響が少ないうちに破産を選択するのが誠実な対応と言えます。
なお、代表者個人としては、破産後、金融機関等からの借入ができなくなることもデメリットとして挙げられます。5年~7年程度で借り入れができるようになることが多い様ですが、破産後の収入状況等を踏まえた審査により借入の可否が左右されるため、明確にどのような状態になれば借入ができるかはわかりません。
4.債権者への対応について
Q 法人を破産させることを債権者にどのように説明すればよいのでしょうか?
A 法人を破産させことは、債権者に影響が大きいため、弁護士が代理人に就任後、書面で通知します(受任通知書)。それまでは、法人側から説明することはせず、債権者には伏せておいてください。
Q 債権者からの督促が厳しく、精神的に参っています。何とか督促を止める方法はありませんか?
A 破産申立を弁護士に依頼すると、受任した弁護士が代理人として債権者に受任通知書発送します。これ以降、債権者からの督促等は代理人弁護士宛になされるため、法人(代表者)には連絡が来なくなり、精神的に楽になります。
Q 法人が破産をすると債権者が自宅に押し掛けてくるのではないかと不安です。
A まず、金融機関はコンプライアンスの問題があるので自宅に押し掛けるようなことはありません。弁護士が発送する受任通知に、今後の連絡は全て法人(代表者)ではなく代理人弁護士宛に行うように記載することから法人に連絡がいくことはほとんどありません。稀に取引先などの担当者が自宅や法人を訪問することがありますが、このような場合は弁護士に連絡をしてもらえれば代わりに対応します。
小説やドラマの影響で債権者が自宅に上がり込んで乱暴な対応をしたり、金目の物を持って行ったりするというイメージを持たれている方もいますが、破産の実務とはかけ離れています。
Q 破産しても支払いを督促してくる債権者がいるのではないでしょうか?
A 破産した場合でも債権の支払を督促するという行為自体はできますが、破産により支払い義務がなくなっていることから、応じる必要はありません。実務的には、破産後に債権者が支払を督促してくることはありません。
また、連帯保証人であった個人は破産により法律上支払い義務がなくなるため、連帯保証人に対して支払いを督促すると、場合によっては支払い義務のないものに支払いを強要したとして、強要罪に当たる可能性もあります。万が一、督促があった場合は、代理人弁護士が警告しますので問題ありません。
Q 長年お世話になった取引先だけは優先して支払いをしたいのですが問題ないでしょうか?
A 破産法により違法な支払いとして否認される可能性があるため問題があります。
債務の支払いは義務の履行であることから、原則、違法にはなりませんが、破産状態にある時点では全債権者に全額の弁済が不可能であり、その中で特定の債権者のみ弁済をすることは破産法により否認される可能性があります。
特定の債権者に優先弁済するのは、当該債権者を優遇したいとの意図と思われますが、その結果、破産手続開始後、破産管財人によりその債権者に対して、否認の請求・訴訟がされる可能性があり、かえって迷惑をかけてしまいます。
5.得意先への対応について
Q 破産する場合でも特定の得意先とだけ取引を続けることはできませんか?
A 破産は事業停止を伴うため、原則として、取引を継続することはできません。もっとも、得意先に迷惑を掛けないよう特定の取引のみ納品を完了したい等、取引対象・期限を限定できる場合は検討の余地があります。当該取引先の納品を済ませるなどして売掛金等の代金を満額で回収した方が経済的に合理性がある場合等は、他の状況も検討した上で一定期間事業を継続する余地もあります。具体的な対応は必ず弁護士にご相談ください。
Q 受注した業務が仕掛中です。破産しても業務を続けることはできませんか?
A 破産法36条は破産手続開始後の事業継続の制度を定めており、理論上は、破産をしても事業を継続することは可能です。したがって、この制度を利用して仕掛中の業務を完了させるという選択肢もあります。
もっとも、破産手続が開始した場合、法人の財産に関する管理処分権は破産管財人に帰属するため、法人の事業に精通していない管財人が事業を継続することは事実上困難であり、実務上、破産法36条による事業継続の制度はあまり利用されていません。
また、事業継続には仕入れ代金・従業員等の給与支払いの原資を確保することが必要ですが、そもそも資金繰りがつかないことから破産を選択することが大半という状況からしても事業継続は困難な事例が多いです。仕掛りの業務が1ヵ月前後で完了するのであれば、むしろ、破産申し立ての時期を調整して、業務完了後に破産の申し立てをするなど対応もありえます。この場合の対応は個々の事案ごとに判断する必要があるため、必ず弁護士にご相談ください。
Q 破産をして事業を停止すると、得意先に迷惑をかけてしまいます。どのように対処したらいいでしょうか?
A 破産により事業を停止した場合、得意先に迷惑をかけることはさけられません。この場合、どれだけ得意先にかかる悪影響を軽減するかということに発想を切り替える必要があります。
具体的な対応は取引の内容を踏まえて決定することになりますが、得意先が代替の取引先と取引を開始する際に取引情報を引きつぐ等の配慮が必要になるでしょう。
6.従業員への対応について
Q 従業員の給与が未払いになっています。優先的に給与を支払うことはできないでしょうか?
A 破産法上、従業員の給与は財団債権・優先的破産債権として、破産手続きにおいて優先的に支払いを受けることができるように手当されています。もっとも、破産手続における支払いには時間がかかるため、給与の遅配状態がながくなってしまいます。
そこで、破産申立前に従業員の給与未払いが少くなるタイミングで給与を支払う等の工夫をすることもあります。
Q 法人に資金はありませんが従業員の給与を支払う方法はありませんか?
A 現時点で給与支払いの資金がない場合でも、売掛金を回収・資産を売却することで資金を捻出し、他方、給与以外の支払いを停止することで、原資を確保する等の方法があります。
また、法人に全く資産がない場合は、独立行政法人労働者健康安全機構の立替払い制度が利用できる場合があります。ただし、解雇予告手当は立替払い制度の対象外のため、未払い賃金がある状態で解雇予告手当が発生する即時解雇をする場合は、解雇予告手当の支払いを優先するなどの工夫が必要です。
7.破産手続について
Q 破産手続の流れを教えてください。
A 破産手続きは、概ね次のような流れで進みます。
- 弁護士に破産申立を委任
- 受任通知を発送
- 破産申立
- 審尋手続
- 破産手続開始
- 管財人面接
- 財産状況報告集会・債権者集会
- 破産手続終了(破産手続廃止・終結)
①から③までの期間は事案により変動します。
③の破産申立から開始決定までの期間は、裁判所の体制によりことなり、小規模庁では破産申し立てから2週間前後、東京地裁では破産申立(③)を受理した日に④の審尋を行い、速やかに破産手続を開始する運用になっています。
破産手続開始(⑤)後、1週間程度で破産管財人と面接を行い、概ね⑤の3か月後に初回の財産状況報告集会・債権者集会が行われます。
債権者への配当が行われない事案では、原則、初回の財産状況報告集会・債権者集会で破産手続が終了(異時廃止)することになります。
破産手続が続行された場合は、3か月後を目安に次回の期日が指定されます。